個人市民税・県民税の定額減税、定額減税調整給付金、令和6年度新たに非課税等となる世帯に対する給付金(よくある問い合わせ)
令和6年度個人市民税・県民税の定額減税、定額減税調整給付金及び令和6年度新たに非課税等となる世帯に対する給付金について、よくある質問を掲載しています。(内容は随時更新していきます。)
調整給付金(不足額給付)(令和6年度実施の定額減税調整給付金(当初調整給付金)に不足がある方などへの給付金)については、こちらをご覧ください。(令和7年8月5日更新)
個人市民税・県民税の定額減税については、こちらをご覧ください。
定額減税調整給付金及び令和6年度新たに非課税等となる世帯に対する給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)に終了しました。
定額減税を踏まえた、令和6年分所得税の確定申告については、「定額減税と確定申告(国税庁ホームページ)」をご覧ください。(令和7年1月20日更新)
Q&Aの一覧
1 定額減税の制度について
Q1-1 定額減税とは何ですか。
Q1-2 定額減税の対象はどのような人ですか。
Q1-3 4人家族で妻と子供2人を扶養している場合の定額減税はいくらになりますか。
Q1-4 令和6年3月に子供が生まれました。定額減税の加算対象となりますか。
Q1-5 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象となりますか。
Q1-6 令和6年2月に就職しました。定額減税の対象となりますか。
Q1-7 令和6年中に藤枝市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。
Q1-8 定額減税が令和6年度個人市民税・県民税から引ききれなかった場合はどうなりますか。
Q1-9 令和5年中の収入がなく令和6年度の個人市民税・県民税は非課税です。定額減税の対象となりますか。
Q1-10 令和6年度の個人市民税・県民税が均等割のみの課税の場合はどうなりますか。
Q1-11 所得税の定額減税はどのようになりますか。
Q1-12 定額減税の適用を受けたことについて、確定申告する必要がありますか。(令和7年1月20日更新)
2 手続き及び定額減税の確認方法について
Q2-1 定額減税を受けるための申請は必要ですか。
Q2-2 定額減税の額を確認したい場合はどうすればよいですか。
Q2-3 確定申告や年末調整で扶養親族の申告が漏れており、定額減税の対象から外れていることが分かりました。どのような手続きが必要ですか。
3 その他
Q3-1 令和7年度も定額減税は行われますか。
Q3-2 福祉制度など他の制度に影響はありますか。
Q3-3 定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。
4 事業者向け
Q4-1 今回の個人市民税・県民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として手続きは必要ですか。
Q4-2 所得税のように個人市民税・県民税の定額減税額を会社(特別徴収義務者)で計算する必要がありますか。
Q4-3 所得税の源泉徴収事務、年末調整事務における定額減税の取り扱いについて知りたい。
Q4-4 定額減税が適用されたのに5,400円の税額があるのはなぜですか。
Q4-5 特別徴収税額が同じ5,400円であるのに、徴収する月が6月分と7月分で異なるのはなぜですか。
Q4-6 従業員が退職(又は就職)により特別徴収できなくなりました。定額減税はどのように扱われますか。
Q4-7 定額減税で税額が減るはずなのに、各月の徴収税額が増えているのはなぜですか。
Q4-8 従業員が定額減税の適用となっているか確認できますか。
5 給付金について
Q5-1 定額減税として引ききれない税額がある場合はどうなりますか。
Q5-2 令和6年度の個人市民税・県民税が均等割のみ課税される場合はどうなりますか。
Q5-3 令和6年度の個人市民税・県民税が非課税の場合はどうなりますか。
6【令和6年度終了】 定額減税の調整給付金(当初調整給付金)について
Q6-1 調整給付とはどのような制度ですか。
Q6-2 調整給付はどのような人が対象ですか。
Q6-3 調整給付はいつもらえますか。
Q6-4 調整給付はいくらもらえますか。
Q6-5 調整給付を受け取るためにはどのような手続きを行ったらよいですか。
Q6-6 調整給付の対象となるか確認したいです。どこに行けばよいですか。また、必要な書類等はありますか。
Q6-7 私は市民税・県民税が非課税ですが、調整給付は受けられますか。
Q6-8 令和6年に子どもが生まれました。調整給付の対象となりますか。
Q6-9 「確認書」はどこに送付されますか。
Q6-10 令和6年分推計所得税額が令和5年分所得税額と異なります。なぜですか。
Q6-11 定額減税調整給付金の宛名になっている親族が死亡した場合は、どのような取り扱いになりますか。
7 【令和6年度終了】令和6年度新たに非課税等となる世帯に対する給付金について
Q7-1 私は、令和6年度分の個人市民税・県民税において、「非課税となった方」・ 「均等割が課税されている方」・「所得割が課税されている方」・「未申告である方」のいずれに該当しますか。
8【令和7年度実施】調整給付金( 不足額給付)について (令和7年8月5日更新)
Q8-1 調整給付金( 不足額給付)とは何ですか。
Q8-2私は調整給付金( 不足額給付)の対象になりますか。
Q8-3 不足額給付は、どこから支給されますか。
Q8-4 令和7年中に藤枝市に転入し住民登録をしましたが、不足額給付は藤枝市から支給されますか。
Q8-5 源泉徴収票の「控除外額」とは何ですか。
Q8-6源泉徴収票の「控除外額」(控除しきれない額)の金額が支給されますか。
Q8-7令和6年度分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか。
Q8-8不足額給付の金額は具体的にどのように決まりますか。
Q8-9不足額給付の支給はいつからですか。
Q8-10受給した不足額給付金は課税の対象となりますか。
Q8-11給与収入と公的年金収入があり、それぞれで定額減税を受けていますが、確定申告の必要はありますか。
Q8-12確定申告書を作成するときに確定申告書第一表の「₍44₎令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」の欄の入力を忘れてしまいました。どうすればいいですか。
Q8-13これから還付申告(医療費控除、住宅ローン控除等)を行った場合でも不足額給付の対象になりますか。
Q&Aの回答
1 定額減税の制度について
Q1-1 定額減税とは何ですか。
A1-1 デフレ完全脱却のための一時的な措置として実施する減税で、納税義務者及びその配偶者を含めた扶養親族(国内居住者に限ります。)1人につき、令和6年分の所得税額から3万円、令和6年度分の個人市民税・県民税所得割額から1万円が控除されます。
Q1-2 定額減税の対象はどのような人ですか。
A1-2 令和6年度の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者が対象です。
ただし、以下に該当する場合は対象となりません。
(1)令和6年度の個人市民税・県民税が非課税の方
(2)令和6年度の個人市民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される方
(3)事務所、事業所、家屋敷に対し個人市民税・県民税の均等割が課税される方
Q1-3 4人家族で妻と子供2人を扶養している場合の定額減税はいくらになりますか。
A1-3 定額減税額は4万円です。
定額減税は、本人に1万円、控除対象配偶者又は扶養親族1人につき1万円を加算して算定します。よって、定額減税額は、1万円(本人)+3人(扶養)×1万円=4万円 となります。
ただし、国内に住所を有しない控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者)は、定額減税の対象から除外します。
Q1-4 令和6年3月に子供が生まれました。定額減税の加算対象となりますか。
A1-4 加算対象となりません。
定額減税は、令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族人数を元に加算額を算定します。令和6年1月2日以降に生まれたお子様については令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族とならないため、定額減税の加算対象となりません。
Q1-5 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象となりますか。
A1-5 令和6年1月1日時点で16歳未満の(平成20年1月2日以降に生まれた)扶養親族(国外居住者を除く)も対象となります。
Q1-6 令和6年2月に就職しました。定額減税の対象となりますか。
A1-6 令和5年分の収入がない方は、定額減税の対象となりません。
定額減税は、令和6年度個人市民税・県民税所得割が課税される方が対象です。どなたかの扶養(被扶養者)となっている場合は、定額減税の対象の扶養者の定額減税に加算されています。
Q1-7 令和6年中に藤枝市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。
A1-7 令和6年度の個人市民税・県民税及び定額減税は、原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で算定されます。
Q1-8 定額減税が令和6年度個人市民税・県民税から引ききれなかった場合はどうなりますか。
A1-8 定額減税しきれない場合は調整給付します。
令和6年度個人市民税・県民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人市民税・県民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を給付(調整給付)します。
調整給付の申請受付については、令和6年10月31日(木曜日)に終了しました。
Q1-9 令和5年中の収入がなく令和6年度の個人市民税・県民税は非課税です。定額減税の対象となりますか。
A1-9 定額減税の対象になりませんが、別途給付対象世帯に該当する場合があります。
定額減税は、令和6年度個人市民税・県民税所得割が課税される方が対象です。なお、どなたかの扶養(被扶養者)となっている場合は、定額減税の対象の扶養者の定額減税に加算されています。
なお、誰にも扶養されておらず令和6年度に新たに非課税世帯となる場合は、別途給付金の対象となる場合があります。給付の申請受付については令和6年10月31日(木曜日)に終了しました。
Q1-10 令和6年度の個人市民税・県民税が均等割のみの課税の場合はどうなりますか。
A1-10 定額減税の適用はありませんが、別途給付対象世帯に該当する場合があります。
令和6年度個人市民税・県民税において、所得割の課税がない場合は定額減税の適用はありません。
なお、令和6年度に新たに非課税又は均等割のみ課税されている方のみで構成される世帯となる場合は、別途給付金の対象となる場合があります。給付の申請受付については令和6年10月31日(木曜日)に終了しました。
Q1-11 所得税の定額減税はどのようになりますか。
A1-11 所得税については、「定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)」をご確認いただくか、管轄の税務署へ電話にてお問い合わせください。
Q1-12 定額減税の適用を受けたことについて、確定申告する必要がありますか。(令和7年1月20日更新)
A1-12 定額減税を踏まえた令和6年分所得税の確定申告については、「定額減税と確定申告(国税庁ホームページ)」をご覧ください。
確定申告手続の要否については、「令和6年分所得税の定額減税 ~確定申告の手続判定フローチャート~ (PDF)」をご確認ください。
2 手続き及び定額減税の確認方法について
Q2-1 定額減税を受けるための申請は必要ですか。
A2-1 申請は必要ありません。
定額減税は、個人市民税・県民税を課税するための資料(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を元に算定します。
Q2-2 定額減税の額を確認したい場合はどうすればよいですか
A2-2 定額減税額は、市民税・県民税・森林環境税の各通知書又は所得課税証明書により確認することができます。
(1)給与からの特別徴収の場合
「令和6年度 給与等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄
(2)普通徴収又は公的年金からの特別徴収の場合
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税及び税額決定通知書」の税額控除欄
詳しくは、「個人市民税・県民税の定額減税について(課税課ホームページ)」をご覧ください。
Q2-3 確定申告や年末調整で扶養親族の申告が漏れており、定額減税の対象から外れていることが分かりました。どのような手続きが必要ですか。
A2-3 対象の扶養親族について令和6年度市民税・県民税申告書によりご申告いただきます。申告手続きについては「【住民税試算システム】市民税・県民税の試算や市民税・県民税申告書の作成ができます(課税課ホームページ)」を参照いただくか課税課市民税係窓口へご提出ください。
令和6年度市民税・県民税及び定額減税を再計算の結果、税額変更又は定額減税が変更となる場合は、税額変更通知書をお送りします。また、税務署で確定申告等を行うことで所得税も減額となる場合があります。
<ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用された方はご注意ください>
ふるさと納税ワンストップ特例制度(寄附金控除の申告特例制度)の適用を受けている場合は、所得税の確定申告書又は市民税・県民税申告書を提出することによりワンストップ特例の適用が受けられなくなります。扶養親族を追加する申告をする場合は、ふるさと納税された寄附金についてもあわせて申告してください。
3 その他
Q3-1 令和7年度も定額減税は行われますか。
A3-1 令和7年度の個人市民税・県民税において、同一生計配偶者※(控除対象配偶者及び国外居住者を除く)を有する納税義務者を対象に定額減税が適用されます。
※以下のいずれにも該当する配偶者を同一生計配偶者といいます。
(1)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えている。
(2)前年12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、納税義務者と生計を一にしている。
(3)合計所得金額が48万円以下である。
(4)青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者でない。
Q3-2 福祉制度など他の制度に影響はありますか。
A3-2 定額減税の取り扱いは各事業により異なりますので、お手数ですが各事業担当部署へお問い合わせください。
Q3-3 定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。
A3-3 ふるさと納税の限度額(所得割額の20%)の算定は、令和6年度の市民税・県民税所得割額は、定額減税前の所得割額を基礎に算定するため影響ありません。
4 事業者向け
Q4-1 今回の個人市民税・県民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として手続きは必要ですか。
A4-1 定額減税に関する特別な手続きは必要ありません。
定額減税を適用した後の税額により特別徴収税額決定・変更通知書が送付されますので、従前のとおり通知の金額どおりに差し引いて納入をお願いします。
Q4-2 所得税のように個人市民税・県民税の定額減税額を会社(特別徴収義務者)で計算する必要がありますか。
A4-2 定額減税額を計算する必要ありません。
定額減税を適用した後の税額により特別徴収税額決定・変更通知書が送付されますので、特別徴収義務者が計算する必要はありません。
Q4-3 所得税の源泉徴収事務、年末調整事務における定額減税の取り扱いについて知りたい。
A4-3 所得税の源泉徴収事務等については、「定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)」をご確認いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。
Q4-4 定額減税が適用されたのに5,400円の税額があるのはなぜですか。
A4-4 定額減税が適用されない個人市民税・県民税の均等割及び森林環境税として納付をお願いします。
個人市民税は、所得額に応じて課税される『所得割』と一定の所得がある場合に一律で課税される『均等割及び森林環境税(以下「均等割等」)』で構成されますが、定額減税は、個人市民税・県民税の所得割のみに適用されますので、定額減税により所得割額が0円となっても均等割等の納付をお願いしています。
Q4-5 特別徴収税額が同じ5,400円であるのに、徴収する月が6月分と7月分で異なるのはなぜですか。
A4-5 定額減税が適用された方は7月分、定額減税の適用が無い方は6月分から徴収となります。
定額減税を適用する場合は、減税後の税額について、6月分を徴収せず7月分から翌年5月分までで納付いただくことになります。一方、定額減税が適用されない方は、従前のとおり6月分から納付いただくことになります。このため、定額減税適用の有無で均等割等の額が同じ5,400円でも徴収月が替わります。
Q4-6 従業員が退職(又は就職)により特別徴収できなくなりました。定額減税はどのように扱われますか。
A4-6 定額減税の額に変更はありません(定額減税に関する特別な手続もありません)。
定額減税適用後の税額について納付方法を変更する形となるため、これまで通り給与支払報告書及び特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出をお願いします。また、年の途中で特別徴収の対象となる場合においては、未納となっている税額について、徴収可能の月分から特別徴収を開始いただくことになります。
Q4-7 定額減税で税額が減るはずなのに、各月の徴収税額が増えているのはなぜですか。
A4-7 定額減税後は6月分を0円とし、徴収回数が減少したことによるものです。
給与からの特別徴収における定額減税は、減税後の税額を7月分から翌年5月分までの11回で均すとされています。このため、各月分の徴収税額が定額減税の額を超える場合は、徴収回数が12回から11回に減少するため1回あたりの徴収税額が増えてしまう場合があります。
【パターン1 徴収税額が変わらない場合の計算例】
減税がない場合 年税額12万円 ÷ 納付回数12回 = 各月の徴収税額1万円
減税がある場合 (年税額12万円 - 定額減税1万円)÷ 納付回数11回 = 各月の徴収税額1万円
【パターン2 徴収税額が変わる場合の計算例】
減税がない場合 年税額36万円 ÷ 納付回数12回 = 各月の徴収税額3万円
減税がある場合 (年税額36万円 - 定額減税1万円)÷ 納付回数11回 = 各月の徴収税額3万1,800円
Q4-8 従業員が定額減税の適用となっているか確認できますか。
A4-8 令和6年5月に発送した当初通知書で確認できます。なお、当初通知以降に変更通知書における定額減税の適用については、該当する従業員に確認いただくか、課税課市民税係までお問い合わせください。
令和6年5月に発送した「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」(当初通知)の従業員別の内訳のうち、定額減税適用者は、6月分の徴収税額が0円で7月分から翌年5月分の徴収税額が記載されています。
5 給付金について
Q5-1 定額減税として引ききれない税額がある場合はどうなりますか。
A5-1 定額減税しきれない場合は調整給付します。
令和6年度個人市民税・県民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人市民税・県民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を給付(調整給付)します。
調整給付(当初調整給付)の申請受付については、令和6年10月31日(木曜日)に終了しました。
Q5-2 令和6年度の個人市民税・県民税が均等割のみ課税される場合はどうなりますか。
A5-2 定額減税の適用はありませんが、別途給付対象世帯に該当する場合があります。
令和6年度個人市民税・県民税において、所得割の課税がない場合は定額減税の適用はありませんが、令和6年度に新たに非課税又は均等割のみ課税されている方のみで構成される世帯となる場合は、別途給付金の対象となる場合があります。給付の申請受付については令和6年10月31日(木曜日)に終了しました。
Q5-3 令和6年度の個人市民税・県民税が非課税の場合はどうなりますか。
A5-3 定額減税の適用はありませんが、別途給付対象世帯に該当する場合があります。
定額減税は、令和6年度個人市民税・県民税所得割が課税される方が対象です。なお、どなたかの扶養(被扶養者)となっている場合は、定額減税の対象の扶養者の定額減税に加算されています。
なお、誰にも扶養されておらず令和6年度に新たに非課税世帯となる場合は、別途給付金の対象となる場合があります。給付の申請受付については令和6年10月31日(木曜日)に終了しました。
6 【令和6年度終了】定額減税の調整給付金(当初調整給付金)について
当初調整給付金の申請受付については、令和6年10月31日(木曜日)に終了しました。
Q6-1 調整給付とはどのような制度ですか。
A6-1 令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・県民税で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)について、給付金が支給されるものです。
Q6-2 調整給付はどのような人が対象ですか。
A6-2 令和6年度分個人市民税・県民税所得割が課税されている方又は令和6年度分個人市民税・県民税の課税内容を基に算出される令和6年分推計所得税額がある方で、定額減税しきれない方(定額減税可能額が減税前税額を上回る方)が、調整給付の対象となります。
ただし、前年の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。
Q6-3 調整給付はいつもらえますか。
A6-3 令和6年9月上旬より順次発送する「確認書」を返送または同封されているQRコードよりオンラインで手続いただき、内容に不備がない場合に給付いたしました。
Q6-4 調整給付はいくらもらえますか。
A6-4 次の計算式で得た金額を給付します。
(1)+(2)の合計額(合計額を万円単位に切り上げて給付)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人市民税・県民税所得割分定額減税可能額-令和6年度個人市民税・県民税所得割額
例)
・納税者のみ(扶養親族がいない)
・推計所得税額が0円
・個人市民税・県民税所得割額が4,500円
の場合
3万円(所得税分定額減税可能額)-0円(令和6年分推計所得税額)=3万円…(1)
1万円(個人市民税・県民税所得割分定額減税可能額)-4,500円(令和6年度個人市民税・県民税所得割額)=5,500円…(2)
35,500円((1)+(2))を1万円単位で切り上げ、4万円(定額減税補足給付金額)を給付
Q6-5 調整給付を受け取るためにはどのような手続きを行ったらよいですか。
A6-5 調整給付の受給手続については、令和6年9月上旬より順次発送する「確認書」等の内容を確認し、確認書に必要事項を記入し、令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)までに返送または同封されているQRコードよりオンラインで手続きしてください。
期限までに返信がない場合は、本給付金の支給はできませんのでご注意ください。
Q6-6 調整給付の対象となるか確認したいです。どこに行けばよいですか。また、必要な書類等はありますか。
A6-6 給付対象となる方には、令和6年9月上旬より順次「確認書」等を発送しますが、対象となるか事前に確認したい場合には、課税課市民税係窓口(市役所庁舎西館2階)に、マイナンバーカード、運転免許証等本人確認できるものを持参の上お越しください。(平日の午前8時30分~午後5時15分)
当初調整給付の対象者の選定は終了しました。
Q6-7 私は市民税・県民税が非課税ですが、調整給付は受けられますか。
A6-7 個人市民税・県民税が非課税の場合でも、令和6年分推計所得税額がある方で、定額減税しきれない方(定額減税可能額が減税前税額を上回る方)は、調整給付の対象となります。
Q6-8 令和6年に子どもが生まれました。調整給付の対象となりますか。
A6-8 令和6年中の扶養親族の追加は、調整給付の対象になりません。調整給付の算出は、令和6年度分(令和5年中)の所得・扶養情報となります。
Q6-9 「確認書」はどこに送付されますか。
A6-9 給付対象となる方には、原則、令和6年度分個人市民税・県民税の納税通知書又は特別徴収税額の決定通知書に記載の住所へ「確認書」等を送付します。
引っ越し、単身赴任、DV等による避難などにより、実際の居所が令和6年度分個人市民税・県民税の納税通知書又は特別徴収税額の決定通知書に記載の住所と異なる場合は、藤枝市給付金コールセンターにお問い合わせください(コールセンターによるお問い合わせの受付は終了しました)。
Q6-10 令和6年分推計所得税額が令和5年分所得税額と異なります。なぜですか。
A6-10 令和6年分推計所得税額とは、個人市民税・県民税の課税資料(令和5年分の所得の内容)から令和6年分の所得税額を推計したものです。また、住宅ローン控除や寄附金控除など所得税の税額控除を反映していないため、令和5年分所得税額とは異なることがあります。
ただし、令和6年度分個人市民税・県民税において、住宅ローン控除が適用されている方については、令和6年分推計所得税額に住宅ローン控除が反映されています。
なお、令和6年分の所得税などが確定した後に調整給付額に不足が生じる方に対しては、令和7年度に追加で給付金を支給する予定となっています。
※令和6年分推計所得税額と令和5年分所得税額が異なる主な要因
1.所得税がかかっている全ての方
復興所得税(税率2.1%)分の額は推計所得税額に含まれていません。
2.住宅ローン控除を申告した方で所得税額が0円でない方
住宅ローン控除額は推計所得税額に反映していません。
3.寄附金控除を確定申告もしくは市民税申告した方(ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けた方は除く)
寄附金控除額は推計所得税額に反映していません。
4.生命保険料控除及び地震保険料控除を受けている方、分離譲渡所得がある方
按分計算にて推計しているため税額が異なります。
Q6-11 定額減税調整給付金の宛名になっている親族が死亡した場合は、どのような取り扱いになりますか。
A6-11 申請前に亡くなられている場合は、受給権がありません。
申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
※確認書の印刷時期の関係で、亡くなられた方宛てに届く場合がありますので、御了承ください。
7 令和6年度新たに非課税等となる世帯に対する給付金について
給付金の申請受付については、令和6年10月31日(木曜日)に終了しました。
Q7-1 私は、令和6年度分の個人市民税・県民税において、「非課税となった方」・ 「均等割が課税されている方」・「所得割が課税されている方」・「未申告である方」のいずれに該当しますか。
A7-1 藤枝市より、令和6年度個人市民税・県民税・森林環境税納税通知書もしくは令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収額の決定通知書(納税義務者用)が届いていない場合は、「非課税となった方」もしくは「未申告である方」に該当します。
各通知書が届いている場合で、「定額減税」及び「定額減税残」と印字されている場合は「所得割が課税されている方」に該当します。印字されていない場合は「均等割が課税されている方」に該当します。
8 【令和7年度実施】調整給付金(不足額給付) (令和7年8月5日更新)
Q8-1 不足額給付金とは何ですか。
A8-1以下の事情により、令和6年度に実施した定額減税調整給付金の支給額に不足が生じた方などを対象に、不足する金額を支給する給付金のことです。
・【不足額給付I】令和6年分所得税実績額など確定した結果、当初調整給付金の支払い額に不足が生じた方には、不足額給付時の調整給付金額と当初調給付金額の差額(※1万円単位)が支払われます。
・【不足額給付II】以下の要件の全てを満たす人は、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)が支払われます。
〇令和6年所得税・令和6年個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円である
〇所得金額48万円を超える人や青色事業専従者・事業専従者(白色)など、税制度上、扶養親族の対象外である
〇低所得世帯向け給付(※)を受給した世帯の世帯主・世帯員でない
※令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
令和6年度新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
詳しくは定額減税調整給付金(不足額給付)についてをご覧ください
Q8-2 私は不足額給付の対象になりますか。
A8-2年末調整や確定申告などで、令和6年分所得税や定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間に差額が生じた方が不足額給付の対象となります。【不足額給付I】
また、事業専従者(青色・白色)や合計所得金額48万円超の方で、過去の低所得世帯向けの給付金や定額減税の対象とならなかった方も、不足額給付の対象となります。【不足額給付II】
不足額給付の対象となる方には、市から給付金額を記載した通知を発送する予定です。
ただし、【不足額給付II】の対象となる方の中には、市が課税情報等から確認しても把握できない方もいます。その場合、対象の方からコールセンター(0570-012-812)へ連絡いただき、申請の手続き等が必要になります。
そちらにつきましては、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
Q8-3 不足額給付は、どこから支給されますか。
A8-3 令和7年度個人住民税を課税している自治体から支給されます。令和7年度個人住民税は、原則として令和7年1月1日現在において住民登録がある自治体で課税され、その後に他の自治体に引っ越した場合でも、課税する自治体は変わりません。なお、個人住民税を課税している自治体と住民登録している自治体が異なる方もいますが、その場合も、不足額給付は課税している自治体から支給されます。
Q8-4令和7年中に藤枝市に転入し住民登録をしましたが、不足額給付は藤枝市から支給されますか。
A8-4 不足額給付を支給するのは、令和7年度個人住民税を課税する自治体(原則は令和7年1月1日に住民登録していた自治体)になりますので、藤枝市からは支給されません。該当する自治体へお問い合わせください。
Q8-5 源泉徴収票の「控除外額」とはなんですか。
A8-5 「控除外額」は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除(減税)しきれなかった額です。源泉徴収票の「控除外額」は、今回実施する不足額給付の額を算出する際に用います。
なお、「控除外額」に記載された金額と不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。
Q8-6源泉徴収票の「控除外額」(控除しきれない額)の金額が支給されますか。
A8-6源泉徴収票の「控除外額」は、今回実施する不足額給付の額を算出する際に用います。
ただし、「控除外額」に記載された金額と不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。
【控除外額=不足額給付とならない例】
- 令和6年の秋に実施された「当初調整給付金」の対象となっていた場合
- 源泉徴収票の記載以外にも収入がある場合
- 扶養親族の合計所得金額が48万円を超えたため、扶養控除が変更になった場合
Q8-7令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか。
A8-7令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されているためです。
令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれておりません。
住民税分の定額減税については、「令和6年度市民税・県民税税額決定通知書」等をご確認ください。
【参考:定額減税可能額の考え方】
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
Q8-8不足額給付の金額は具体的にどのように決まりますか。
A8-8【不足額給付I】に該当する方
「実際の定額減税しきれない額」(注1)-「当初調整給付」
(注1)実際の定額減税しきれない額=(ア)と(イ)の合算
(ア)所得税分の定額減税しきれない額(※0円以下の場合は0)
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税
(イ)個人住民税分の定額減税しきれない額(注2)(※0円以下の場合は0)
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
(注2)個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更生・扶養更生等がない場合金額に変更はありません。
【不足額給付II】に該当する方…原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
Q8-9不足額給付の支給はいつからですか。
A8-9令和7年8月下旬に対象者へ通知を送付し、9月下旬から順次支給を予定しています。具体的な時期等は、決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
Q8-10受給した不足額給付金は課税の対象となりますか。
A8-10「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差押えの対象とはなりません。
Q8-11給与収入と公的年金収入があり、それぞれで定額減税を受けていますが、確定申告をする必要はありますか。
A8-11不足額給付の算定においては影響がないため、給与収入と公的年金収入で重複して定額減税の適用を受けていることだけをもって、所得税の確定申告を行う必要はありません。
ただし、従来どおり、「給与の収入金額が2,000万円を超える方」や「1か所から給与の支払を受けている方で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える方」など、一定の要件を満たす場合は所得税の確定申告をする必要があります。
詳しくは「国税庁ホームページ 令和6年分確定申告特集『申告の流れ、申告が必要な方など」をご確認ください。
Q8-12確定申告書を作成するときに確定申告書第一表の「(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」の欄の入力を忘れてしまいました。どうすればいいですか。
A8-12令和7年3月17日までに行った確定申告の内容が誤っていた場合に必要な手続については、「国税庁ホームページ【申告書が間違っていた場合】」をご確認ください。
Q8-13これから還付申告(医療費控除、住宅ローン控除等)を行います。不足額給付をもらえますか
A8-13要件を満たせば支給の対象となります。還付申告したうえで、申請締切日までに必要書類とともにオンライン申請をしていただくか、申請書と必要書類を郵送で提出してください。
関連リンク
お問い合わせ
〇不足額給付に関すること
課税課 市民税係(藤枝市不足額給付金 コールセンター)
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:0570-012-812
〇個人住民税の定額減税に関すること、調整給付に関すること、住民税非課税世帯等に対する給付に関すること
課税課 市民税係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3187

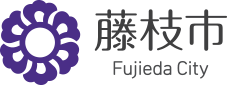

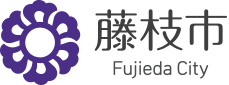
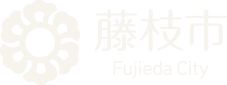




更新日:2024年08月05日