第19回 “魂の俳人”藤枝市村越化石俳句大会の入賞作品が決定しました

第19回"魂の俳人”藤枝市村越化石俳句大会の入賞作品が決定し、令和5年12月10日(日曜日)表彰式を開催しました。
本大会は、魂の俳人と呼ばれ、ハンセン病を患いながらも俳句界に多大な実績を残した村越化石を顕彰する俳句大会です。化石の俳句の世界を理解するとともに、子どもから大人まで俳句に親しみ、楽しんでもらい、俳句文化の振興を図ることを目的に開催しています。
今大会は、市内の小、中学生から全国の一般の部まで、合計3,933句の応募がありました。入賞作品は下記のとおりです。
今後、入賞作品の展示会を以下の日程で巡回展示いたします。ぜひお近くの会場でご覧ください。
|
1月9日 |
火 |
~ |
1月22日 |
月 |
藤枝市役所 玄関ホール |
|
1月22日 |
月 |
~ |
1月31日 |
水 |
生涯学習センター ロビー |
|
2月5日 |
月 |
~ |
2月13日 |
火 |
駅南図書館(BiVi藤枝3階) 注:月曜休館 |
| 2月13日 | 火 | ~ | 2月27日 | 火 |
藤枝市岡部支所分館 玄関ロビー |
村越化石賞(大串 章選)
(小学校の部)佐々木 海琉 <青島北小学校6年>
海の家風鈴たちのオーケストラ
【講評】
海の家に風鈴がたくさん並んでいる。鉄風鈴や貝風鈴など音色もさまざま。まるで管楽器や打楽器による大合奏のよう。「風鈴たちのオーケストラ」とはうまく表現しましたね。素晴しい。
(中学校の部)疋野 ももこ <青島中学校2年>
せみしぐれ魂燃える部活動
【講評】
蟬が鳴き立てる夏の暑い日、魂を燃やして部活動に励んでいる。部活動と言うと運動系の野球やテニス、文化系の吹奏楽など思うが、掲句の部活動は何だろう。何れにしてもその努力に拍手!
(一般の部)椋本 信枝 <藤枝市水上>
共白髪となりて花野の風をきく
【講評】
長年連れ添い、共白髪となった夫婦が花野を歩いてゆく。萩・桔梗など秋の七草のほか、名を知らない草花もいろいろ咲いている。穏やかで広々とした花野を歩いてゆくと、さまざまな事を思い出し懐かしい。「花野の風を聞く」が言い得て妙。
市長賞(大串 章選)
(中学校の部)伊藤 楽 <藤枝中学校1年>
鮎はねて魚道の水がすきとおる
【講評】
鮎が跳ねあがり川の水が透き通って見える。明るく健やかな光景である。鮎は春になると川を遡り、秋には上流の瀬で産卵する。因みに、「魚道」は鮎の遡上を助けるために設けられた工作物。
(一般の部)武藤 洋一 <群馬県前橋市>
よく通る卒寿の声や稲の花
【講評】
輝く稲の花の向こうから卒寿翁の声が聞こえてくる。かなり離れているがはっきり聞こえる。「卒寿の声」が「よく通る」とは素晴らしい。因みに、声がよく通るとは、周囲に雑音が多くても聞き取りやすく、距離が離れていても内容が分かること。
教育長賞(関森 勝夫選)
(小学校の部)竹嶋 優璃 <葉梨小学校3年>
ほご犬となかよくなれた夏休み
【講評】
保護犬を引き取ったばかりは家族になつかなく、苦労していたのだが、日がたつにつれて心を開くようになり、夏休みの終わる頃にはすっかり仲良くなれたという。そのことが夏休みの何よりの成果だったと喜んでいる。この努力を賛えたい。動物愛護の優しい家庭環境も受け止められる。
(一般の部)野上 卓 <東京都世田谷区>
おぼろめく島の着陸誘導灯
【講評】
春が早い南国の島の空港。着陸態勢に入り高度を下げて行く機内の窓から見下した景であろう。滑走路の誘導灯がおぼろに点点と列を成して見えたのである。明日から始まる島での出会いに、作者の期待感がたかぶっていくことが感受される。
文化協会会長賞(関森 勝夫選)
(小学校の部)山下 蒼馬 <藤枝中央小学校2年>
セミがとぶたものむこうの大空へ
【講評】
幹にとまった蝉を捕えようと、慎重にたも(網)をかぶせたのだが、蝉は一瞬にしてたものすきまから逃げてしまった。その生生とした姿を見上げている作者の姿が目に浮かぶ。「大空へ」の表現から自由を得た蝉のよろこびの感情さえもが受け止められる。
(中学校の部)出雲 蒼大<岡部中学校2年>
夏祭りいろんなにおいが入り混じる
【講評】
祭の会場である神社への参道には多くの屋台が並び、食べ物を売っており、その臭いや混雑のひといきれが混り合って強く漂っている。混り合った物のにおいによって祭の夜の盛況ぶりが表現された。祭の具体的な描写はないが、多くの人々が体験していることでもあるので納得出来よう。
参考までだが、江戸時代の句に「市中は物のにほひや夏の月 凡兆」がある。京の下町の盛況ぶりを雑多な匂いによって捉えている。
入選者
(小学生の部)
長谷川 蒼樹(藤枝中央小3年)「炎天下走るぼくたち風になる」
藤原 拓馬 (広幡小3年) 「夏休みのこるしゅくだいみないふり」
石上 春樹 (青島小5年) 「雨蛙水を飛び出し旅に出る」
木村 美月 (広幡小5年) 「水草のすき間にのぞくメダカの子」
(中学生の部)
中村 愛菜(藤枝中1年) 「富士山が入道雲からこんにちは」
和田 采鈴(青島北中1年) 「夏の日の思い出光る日記帳」
今村 駿汰(藤枝中3年) 「汗だくの父にかけたい金メダル」
(一般の部)
大石 俊彦(藤枝市藤岡) 「哀調も一瞬混じる蟬時雨」
毛利 喜子(愛媛県喜多郡内子町)「波のプール子等いつせいに浮き上がる」
加用 富夫 (藤枝市仮宿) 「健在の母校の古木蟬しぐれ」
甲斐 ゆき子(静岡県富士宮市) 「湿原にさび色の草秋の風」
岸部 吟遊(秋田県能代市) 「走り書きの母の追伸つくつくし」
選者
大串 章氏(俳誌「百鳥」主宰、村越化石氏と同じく大野林火氏に師事、朝日新聞俳壇・愛媛新聞俳壇選者。俳人協会会長、日本文藝家協会理事、日本現代詩歌文学館常任理事。第九回俳人協会評論賞受賞、第四十五回俳人協会賞受賞)
関森 勝夫氏(俳誌「蜻蛉」主宰、村越化石氏と同じく大野林火氏に師事、静岡県立大学名誉教授、俳人協会顧問、俳人協会静岡県支部顧問、国際俳句交流協会評議員、日本文藝家協会会員、日本詩歌文学館評議員)

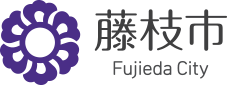

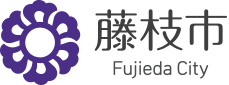
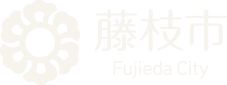


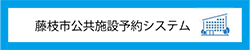




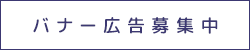
更新日:2023年12月15日