第20回 “魂の俳人”藤枝市村越化石俳句大会の入賞作品が決定しました

第20回"魂の俳人”藤枝市村越化石俳句大会の入賞作品が決定し、令和6年12月8日(日曜日)表彰式を開催しました。
本大会は、魂の俳人と呼ばれ、ハンセン病を患いながらも俳句界に多大な実績を残した村越化石を顕彰する俳句大会です。化石の俳句の世界を理解するとともに、子どもから大人まで俳句に親しみ、楽しんでもらい、俳句文化の振興を図ることを目的に開催しています。
今大会は、市内の小、中学生から全国の一般の部まで、合計3,688句の応募がありました。入賞作品は下記のとおりです。
今後、入賞作品の展示会を以下の日程で開催いたします。ぜひお近くの会場でご覧ください。
特別賞受賞句の展示会
|
1月6日 |
月 |
~ |
1月20日 |
月 |
藤枝市役所 玄関ホール ※1月20日は正午まで |
|
1月21日 |
火 |
~ |
1月29日 |
水 |
生涯学習センター 展示ロビー |
|
2月4日 |
火 |
~ |
2月14日 |
金 |
藤枝市岡部支所分館 玄関ロビー ※月曜日休館 |
| 2月18日 | 火 | ~ | 2月24日 | 月 |
駅南図書館(BiVi藤枝3階) |
村越化石賞
(小学校の部)伊逹 千温 <西益津小学校6年>
夏祭り屋台のトンネル光ってる
【講評】
参道の両側に電灯をともした屋台が並んでいる。その様子を「屋台のトンネル」ととらえた表現がすぐれている。夏祭りのにぎやかさ、作者の心の躍動感も受け止められる。
(中学校の部)増田 愛子 <藤枝中学校1年>
氷柱から滴る水の澄んだ音
【講評】
厳冬の早朝の一景。朝陽がさし、とけたつららの水の一音一音が高くひびく。その音に空気の冷めたさが強く感じられたのである。「澄んだ音」に凍てた朝の静寂さが表現された。
(一般の部)後藤 むつ子 <伊豆市>
手の先に夜明けてゐる盆踊
【講評】
山深い村での盆踊り。星空の下で夜を徹して続く。参加者全員は時間の経過など気にしない。踊りの最中、ふと所作の手先が明るくなっているのに気付き、夜明けを受け止めたのだ。一夜の充実した楽しさが受け止められる。
市長賞
(小学校の部)齊藤 咲来 <高洲小学校3年>
風りんの音聞きながら玉ろのむ
【講評】
涼しい風が入り、風鈴の音がひびく座敷で一服の玉ろ茶をいただく。気持が落ち着く。改めて心地いい風鈴の音に耳を傾ける。外の暑さを忘れ、心穏やかにくつろぐ作者の姿が見える。
(中学校の部)塚本 歩花 <広幡中学校3年>
新緑がまぶしく揺れる嵐山
【講評】
修学旅行での所感。古都の名所の山々が新緑に輝いてまぶしい。初めて体験する名所への心弾みが「まぶしく揺れる」の表現に受け止められる。「嵐山」の地名が働き、句に動きが出る効果をもたらせた。
(一般の部)千葉 信子 <千葉県千葉市>
なによりも水の切れ味水団扇
【講評】
「水団扇」は、水に耐えるように団扇の表面に艶うるし等を引いたもの。井戸水などをふりかけて煽ぐ。産地は奈良等。夕涼みの折、水団扇を使うと、冷たい水がぱらぱらと皮膚に当り、その冷たさが一瞬ながら心地良い。一と昔前の夏の生活をなつかしむ気持ちが表出した。
教育長賞
(小学校の部)山﨑 琉允 <岡部小学校3年>
バッタ見てぼくもとびたい青い空
【講評】
野原でバッタに出会う。近付くと一瞬にして高く飛び上がった。その様子を見、作者も空を飛んで見たい、と思ったのである。青く広い空へのあこがれが表現された。
(中学校の部)下田 さくら <瀬戸谷中学校3年>
負けないで巣立ちのつばめに声掛ける
【講評】
巣立ったばかりの燕の頼りない行動を見て、思はず声援を送ったのである。これからもいろいろな困苦を乗り越える勇気を持てと。作者の小動物への優しい情愛が表出している。
(一般の部)鈴木 恵理 <藤枝市善左衛門>
母と祖母寄り添う背中花火咲く
【講評】
花火大会を家族で楽しんでいた時の一場面を捉えた。母と祖母の寄り添った背後に居た作者は、その穏やかな姿に引き付けられ心が和んだのである。一瞬の花火より美しいと眺めていたに違いない。
文化協会会長賞
(小学校の部)増井 夏菜 <高洲小学校4年>
かぶりつく手からはみだすもも一つ
【講評】
「手からはみ出す」の表現によって、大きく見事な桃であることがわかる。味も甘くおいしかったに違いない。
(中学校の部)良知 花音<西益津中学校3年>
うぐいすがひとりさびしく仲間呼ぶ
【講評】
高原などで夏に入っても鳴いているうぐいすをよんだ句だと思われる。春と違って一匹で大きく鳴いていることが多い。その様子をさびしいので仲間が集まって欲しい、と呼んでいると感じ取ったのである。感情移入の句。作者も友達を作りたいと思っていたのであろう。
(一般の部)菊井 えん <藤枝市与左衛門>
田の隅の余り苗にも雨等し
【講評】
「余り苗」は田植の時に余った苗のこと。田植の終わった田の隅にかたまって植えられていることが多い。必要が失くなったものでも農家の人にとっては捨てがたいものに違いない。「雨等し」は簡明な表現ではあるが作者の心情が強く表出した。この世に多く存在する格差差別について考えさせられる。
市制施行70周年記念賞
(小学生の部)
青嶋 奏汰 (青島小5年) 「思い出はひやけあとでもよみがえる」
吉本 知紗 (青島東小3年) 「しゃくとり虫おりるのこわくてまよってる」
増田 蘭珠 (高洲小4年) 「むかえ火と同じ火でさくにわ花火」
(中学生の部)
岩瀬 恭二(藤枝中1年) 「蝉時雨時に沈黙風の音」
玉木 文也(青島中3年) 「川の中光をのせる山女の背」
青木 花綸(青島北中1年) 「日本勝て送る声援セミに勝つ」
入選者
(小学生の部)
山下 蒼馬(藤枝中央小3年) 「たもよりもあつい夏からにげる虫」
森田 愛乃心 (西益津小5年) 「炎天下暑さ忘れるイルカショー」
秋山 元輝 (葉梨小3年) 「プール行こうぼくよりはしゃぐおじいちゃん」
三好 希花 (葉梨小5年) 「さつまいもぱかっと中身月のよう」
佐藤 建晴 (高洲小6年) 「川沿いを一緒に風切る赤とんぼ」
(中学生の部)
寺岡 真弓(藤枝中2年) 「朝焼けの湯船からみる雪景色」
岩﨑 大河(青島中3年) 「夕焼けでそまる田んぼにただひとり」
杉浦 紘希(葉梨中2年) 「夏の風愛犬はしゃぐ軽井沢」
牧野 鼓次郎(葉梨中3年) 「風の声すき間に響く冬の部屋」
(一般の部)
毛利 喜子(愛媛県喜多郡内子町) 「早送りのごとく蜥蜴の逃げ惑ふ」
高木 春夫(藤枝市志太) 「貧乏のはなし賑やか日向ぼこ」
鈴木 みちゑ (浜松市中央区) 「よく動く手足を褒めて踊りけり」
加用 富夫(藤枝市仮宿) 「立秋や吾にも小さき志」
堂本 房子(藤枝市与左衛門) 「祭櫓朝一番の風に組む」
平野 ローズ(浜松市中央区) 「新しい繋がりできる文化祭」
瀬東 千恵子(石川県白山市) 「小鳥来る牛首紬織る窓辺」
選者
関森 勝夫氏(俳誌「蜻蛉」主宰、村越化石氏と同じく大野林火氏に師事、静岡県立大学名誉教授、俳人協会顧問、俳人協会静岡県支部顧問、国際俳句交流協会評議員、日本文藝家協会会員、日本詩歌文学館評議員)

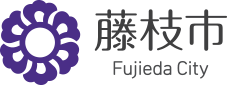

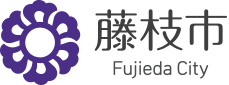
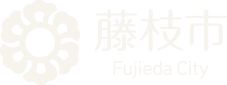



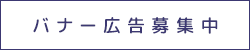
更新日:2024年12月08日