脳脊髄液減少症について
脳脊髄液減少症とはどのような病気なのか
脳脊髄液が漏出することで減少し、頭痛やめまい、吐き気、耳鳴り、不眠や記憶障害などの症状が出て日常生活に支障が生じる病気です。原因は、交通事故の衝撃やスポーツ外傷、階段からの転落、出産などです。積極的な水分摂取や横になって安静を保つことで症状が改善する場合もあります。ご本人は大変苦しいのに周りの理解が得られにくい病気です。
どのような症状がでてくるか
痛み
急性期は起きていると頭痛が強く、横になるとおさまるのですが、慢性期になると横になっても頭痛がおさまらないことがあります。多くは鎮痛剤の効果が乏しく頭痛以外に頸部痛、背部痛、腰痛、手足の痛みもあります。
脳神経症状
耳鳴り、聴覚障害、めまい、ふらつきなどの平衡感覚の異常やピントが合わない、光がまぶしい、視力低下などの目の症状が出ます。顔面痛や嚥下障害や味覚・嗅覚異常が見られる場合もあります。
自律神経症状
微熱、動悸、呼吸困難、胃腸障害、頻尿など
高次脳機能障害
記憶障害、思考力・集中力が極度に低下
その他
極度の倦怠感、疲労感、睡眠障害など気圧の変化に応じて症状が変化するために症状は天気に左右されます。
診断や治療はどのようにして行なうか
急性期は水分摂取と安静横臥で自然治癒する可能性がありますが、上記のような症状が長く続くようでしたら、専門医(主に脳神経外科)の受診をお勧めします。
平成28年4月から保険適応となっているブラッドパッチ療法(ブラッドパッチ(硬膜外自家血注入)療法とは、髄液が漏れている周辺に患者自身の静脈血を注入し、その血液が固まることで漏れを塞ぐ治療法です。)が有効な場合もあります。
外部リンク
静岡県ホームページ外部リンク
特定非営利活動法人 脊髄液減少症患者・家族支援協会外部リンク
脳脊髄液減少症・子ども支援チーム外部リンク

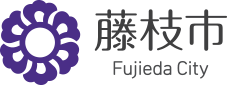

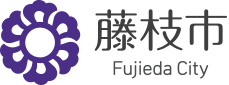
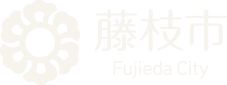




更新日:2024年12月24日