令和7年度文化体験教室【謡曲】を開催しました
謡曲の謡(うたい)や仕舞(しまい)を練習しました
令和7年6月29日(日曜日)に生涯学習センターにて、「文化体験教室」の謡曲<宝生流>教室がスタートしました!講師は静岡掬水会が務めます。
謡曲とは、能楽で使用される詩歌・文章のことで、それに節(ふし)をつけて声に出して謡うものを「謡(うたい)」といいます。また、能の中の一部を抜粋し、謡に合わせて舞う形式のものを「仕舞(しまい)」と呼びます。今年度の教室は、昨年度から引き続き参加している方が多かったため、初回から講師が一人ひとりに付き添い、それぞれの演目に合わせて仕舞の指導を行いました。


参加者は、自分が披露する演目の仕舞を繰り返し練習し、扇の持ち方や角度、足の出し方といった所作の細部にわたって教わっていました。手足を動かしながら、同時に口では謡を唱えなければならないという難しさもあるなか、小学生から一般の方まで、皆さん真剣に集中して取り組んでいた姿が印象的でした。


講師の話によれば、謡曲(能楽)は室町時代に大成された伝統芸能で、題材には『平家物語』のような平安~鎌倉時代の歴史物語や、『羽衣』などの伝説・説話が多く取り上げられるそうです。使用される言葉は古語であり、さらに独特な節回しが加わるため、覚えるのが難しいとされています。それでも参加者は苦戦しながらも、講師と共に繰り返し練習を重ね、ひとつひとつ丁寧に取り組んでいました。

今後の予定について
今後、10月の市民文化祭と11月の文化体験教室合同発表会での発表に向けて、全10回の練習に励みます。発表の当日は、参加者たちが体験教室を通して学んだ成果を披露します。入場は無料ですので、是非、会場までお越しください!

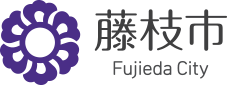

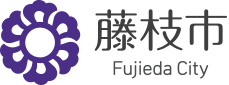
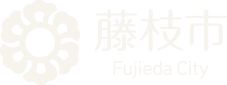




更新日:2025年07月08日