朝比奈玉露名人による朝比奈玉露承継塾を実施しました!
令和7年朝比奈玉露承継塾
【内容・日程】
第1回朝比奈玉露の魅力について(4月5日実施)
第2回被覆作業(4月16日実施)
第3回摘採(手摘み)・荒茶製造(5月11日実施)
第4回剪枝(6月6日実施)
第5回摘心(11月29日実施)
【目的】
現在「朝比奈手摘み本玉露」は、生産者の高齢化や後継者不足をはじめ、摘み子の減少などに伴い、生産量が年々低下しています。本市の宝である「朝比奈手摘み本玉露」を後世に残し、伝統的な玉露生産を承継するため、「朝比奈手摘み本玉露」生産名人が講師となり、全5回のカリキュラムで生産技術などを伝授します。
【玉露とは】
茶園全体を菰(コモ)や寒冷紗(かんれいしゃ)で3週間程覆い、日光を遮ることで旨み成分を凝縮させます。また、朝比奈玉露は年に一度だけ、手作業で一枚一枚丁寧に茶葉を摘み取るため、生産量が少なく、貴重で高価なお茶となります。
【美味しい玉露の淹れ方】(例)
旨みの強い朝比奈玉露は、一度沸騰させたお湯を40℃ほどまで冷まし、茶葉3グラムに対して20cc注ぎ約2分待つと、濃厚で贅沢な旨みを感じることができます。2煎目は、50度ほどのお湯にて同様に2分ほど待つと美味しく味わえます。
水出しでも旨みを堪能することができます。フィルターインボトル(750ccタイプ)に茶葉20グラムを入れ、2時間ほど待ち、軽く振ってから飲むと美味しくいただけます。同じ茶葉を使用していても、振る回数によって味は変わってきますので、自分好みの味をぜひ探してみてください。
補足:飲み始めてから茶葉を抜かずに置いておいたり、強く振りすぎると味が濃くなったり、渋み成分がでてきます。一度に飲まない場合には、抽出されたお茶(茶葉は入れない)を別の容器へ移しておくと味が安定します。当日~翌日を目安にお早めに飲み切ることをおすすめします。
第1回朝比奈玉露の魅力・植栽について
手摘みした朝比奈玉露の品質の高さや煎茶と玉露の違いとして被覆の有無や遮光日数などを学びました。
実際につゆ茶(朝比奈玉露を堪能する飲み方)や急須で淹れた朝比奈玉露を飲み比べた受講生からは、旨みが凝縮された味に驚きの声が上がりました。
植栽では、お茶の葉を傷つけないよう根元から丁寧に持ち上げました。
また、藁を同じ方向に並べ水が流れやすいようにすることで良質な土壌づくりをすることなどを学びました。
植栽の様子
第2回被覆について
一般的に煎茶は被覆をしないこと、かぶせ茶やてん茶(抹茶の原料となる茶葉)では、直接茶畑(直掛け)に寒冷紗をかけること。朝比奈玉露では茶畑の上に棚をつくり間接的に被覆することや遮光日数などの違いを学びました。
実際に被覆作業をする中で、日光が当たらないようにしっかりと寒冷紗で覆うことや、腕を上げながらの作業、細かな作業があり農家さんの労力についても触れることができました。


第3回手摘み・荒茶製造について
煎茶を手摘みする時の一芯二葉とは異なり、「こき摘み」と呼ばれる玉露特有の摘み方で根元から新芽(柔らかい葉)を全て摘み取ります。
生葉から荒茶になるまでの製造工程や各工程におけるこだわりの技術を学びました。
荒茶製造について
第4回剪枝について
「剪枝」とは、茶摘みの終わった茶園の茶樹を短く刈り揃える作業。剪枝をすることで、新芽が太くなり、茶の品質が良くなると言われています。
今回は機械を使用し茶樹を膝ほどの高さに刈り揃えました。
第5回摘心について
「摘心」とは、茶枝の伸びた先端近くの部分を剪定する作業。摘心をすることで、収穫量の増加や、新芽の大きさのバラつきを抑えたり、茶の品質が良くなると言われています。自然仕立ての手摘み玉露園で、剪定鋏を使用し1本1本切り落としました。

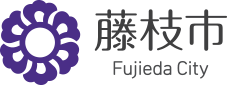

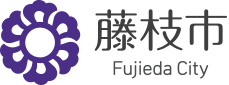
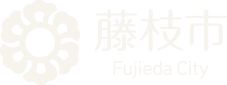














更新日:2025年12月19日