令和6年度
第6回(令和7年3月5日)
 本年度最後の開催となる第6回地域防災指導員連絡会を3月5日に開催しました。
本年度最後の開催となる第6回地域防災指導員連絡会を3月5日に開催しました。
初めに、2月15日に実施された視察研修について、事務局より報告。視察研修に参加した会員からは「福島の教訓を受けて、高台に電源車を置くなどして二重、三重に対策がされていた。」「原子炉は停止しているが、24時間5人態勢で管理していることを初めて知った。」などと感想が発表されました。
その後、令和7年度静岡県・焼津市・藤枝市総合防災訓練について、事務局より説明があり、自主防災会の訓練方法は、令和7年4月から令和8年1月までに最低1回の防災訓練の実施を自主防災会長に依頼していること。県と市が連携して実施する訓練については、現段階の訓練(案)であるため、訓練に参加していただく防災関係機関等と打ち合わせを実施し、訓練の詳細が決定次第、この連絡会などで報告させていただくことになりました。
令和7年度最初の連絡会は、令和7年5月頃を予定しています。
資料
浜岡原子力発電所視察研修について(報告) (PDFファイル: 94.5KB)
令和7年度静岡県・焼津市・藤枝市総合防災訓練について (PDFファイル: 252.7KB)
第5回(令和7年2月15日)
 2月15日、第5回地域防災指導員連絡会(視察研修)を開催し、「浜岡原子力発電所」を視察しました。
2月15日、第5回地域防災指導員連絡会(視察研修)を開催し、「浜岡原子力発電所」を視察しました。
初めに浜岡原子力館で日本のエネルギー事情や浜岡原子力発電所の概要、福島第一原子力発電所の事故の概要、浜岡原子力発電所の安全対策などの説明を受けました。その後、厳重に警備が行われている浜岡原子力発電所の敷地内に入り、防波壁や原子炉建屋に設置されている水密扉、取水槽から敷地内への海水流入を防ぐ壁など、浜岡原子力発電所で行われている安全対策の詳しい説明を受けました。
また、5号機では原子炉建屋内に入り中央制御室や燃料プールなどを見学。最後に万が一災害が発生した場合に本部となる災害対策室を見学させていただき、浜岡原子力発電所で行われている訓練などの説明を受けました。
参加した人からは「テレビで放映されていること以上に安全対策が行われていた。安全対策などの詳しい説明を聞くことができ、実際に見学することの重要性を感じた」と話してくれました。
視察研修の報告は、3月5日に予定している第6回で行う予定です。
第4回(令和6年12月18日)
 12月18日、第4回地域防災指導員連絡会を開催。12月1日に実施した地域防災訓練の振り返りとして、初めにメイン会場での訓練について、これまで岡部中学校指定避難所で避難所開設訓練が実施できていなかったこともあり、参加した人から「実際は多くの人が来ると想定されるのでしっかり準備したい」「繰り返し訓練していくことが必要」などの感想があったとの報告がありました。その後、各地区で実施された地域防災訓練(主に避難所開設・運営訓練)について、実施状況の報告や意見交換が行われました。 また、南海トラフ地震臨時情報発表時の振り返りでは、藤枝地区の自主防災会で南海トラフ地震臨時情報のチラシを全戸配布し啓発を図ったとの報告がありました。
12月18日、第4回地域防災指導員連絡会を開催。12月1日に実施した地域防災訓練の振り返りとして、初めにメイン会場での訓練について、これまで岡部中学校指定避難所で避難所開設訓練が実施できていなかったこともあり、参加した人から「実際は多くの人が来ると想定されるのでしっかり準備したい」「繰り返し訓練していくことが必要」などの感想があったとの報告がありました。その後、各地区で実施された地域防災訓練(主に避難所開設・運営訓練)について、実施状況の報告や意見交換が行われました。 また、南海トラフ地震臨時情報発表時の振り返りでは、藤枝地区の自主防災会で南海トラフ地震臨時情報のチラシを全戸配布し啓発を図ったとの報告がありました。
第5回は、2月15日に視察研修として浜岡原子力発電所を見学することになりました。
資料
【資料1】令和6年度地域防災訓練について (PDFファイル: 182.6KB)
第3回(令和6年10月30日)
 台風等の影響で延期となっていた第3回地域防災指導員連絡会を10月30日に開催しました。
台風等の影響で延期となっていた第3回地域防災指導員連絡会を10月30日に開催しました。
初めに、広報ふじえだ11月5日号とともに全世帯に配布する「ハザードカルテ」の作成方法を学ぶために「わたひな普及員養成講座」を実施。「わたひな」とは、県が行う事業の「わたしの避難計画」の略であり、本市では令和2年度より「ハザードカルテ」として同様の事業を実施しております。
今回、全戸配布するハザードカルテは、避難のタイミングや情報収集手段を記載する欄を設けるなどの改良を加えました。今回、「ハザードカルテ」の作成方法を学んだ皆さんには、地元での普及活動を依頼しました。
連絡会では、事務局から8月下旬の台風10号の被害状況や12月の地域防災訓練における岡部中学校(メーン会場)の訓練について情報共有するとともに、1月に予定している防災研修会の申込方法等をお知らせしました。
資料
【資料1】台風10号に伴う降雨による避難指示の発令について (PDFファイル: 108.5KB)
【資料2】地域防災訓練について (PDFファイル: 152.6KB)
第2回(令和6年7月17日)
 7月17日、各地区の代表者25名の皆さんにご参加いただき、第2回地域防災指導員連絡会を開催いたしました。
7月17日、各地区の代表者25名の皆さんにご参加いただき、第2回地域防災指導員連絡会を開催いたしました。
連絡会に入る前には、県の防災人材育成事業で昨年12月に「被災地訪問研修」に参加した、寺澤さん(島田樟誠高校3年)から、私の体験したことを多くの皆さんに伝えたいとの要望を受け、東日本大震災の被災地を訪問した経験をお話しいただきました。
寺澤さんは、学校防災のあるべき姿として、
- 自分だったらどう行動してどこに避難するかを考えること
- 周りの意見ではなく自分で考えること
- 最悪を常に想定して訓練すること
が非常に大切であること、今後は、今回経験したことを多くの皆さんに伝えていきたいと話してくれました。
連絡会では、地域防災連絡会・避難所運営委員会について、会員が所属する地区の状況が報告され、避難所運営委員会の開催・運営マニュアルの見直し状況とともに、避難所開設・運営訓練に向けた取り組みの報告がありました。
また、自主防災会の総合防災訓練の計画については、市からメーン会場の訓練内容等の説明を行うとともに、会員からは、自主防災会毎実施される防災訓練の計画を報告していただきました。その中で、総合防災訓練では、「昨年より対象者を増やして夜間訓練を実施する。」「本年度は数年ぶりに昼間の訓練を実施する。」など、地域の実情に合わせた訓練の実施予定を報告いただきました。訓練の様子や実施結果については、次回の地域防災指導員連絡会の際に共有を図る予定です。
資料
学んだことを地域に還元し 多くの人たちに伝えたい ~3.11の教訓を経て~ (PDFファイル: 7.5MB)
第1回(令和6年5月8日)
新規メンバーを迎え、第1回地域防災指導員連絡会を開催
 5月8日、令和6年度最初の地域防災指導員連絡会を開催しました。
5月8日、令和6年度最初の地域防災指導員連絡会を開催しました。
連絡会では、委員の約半数が交代したことを受けて、養成講習会実施や連絡会発足の経緯を紹介。その後、本年度の防災事業の概要の紹介をするとともに、総合防災訓練基本計画の説明が行われました。
委員の皆さんからは、「能登半島地震が発生し市民の皆さんの防災意識が高まっている。このタイミングを逃さないように市が進めるわが家の地震対策3本柱や感震ブレーカーの設置などを、住宅密集地などを重点的に実施したほうがいい」「昨年の連絡会で市内の住宅耐震化率が93%と聞いている。一見高いように感じるが地域性があると思われるので、市民が危機感を感じさせることができるように展開してほしい」などと活発な意見が出されました。
また、今後の連絡会について、指導員同士の各地域の課題解決に向けた意見交換がしたいとの委員の意見を受けて、次回の連絡会で各地域の課題を持ち寄り、意見交換会を実施することとなりました。
資料
【資料1】地域防災指導員連絡会の概要 (PDFファイル: 266.9KB)
【資料2】令和6年度防災対策事業 (PDFファイル: 578.3KB)
【資料3】令和6年度総合防災訓練(基本計画) (PDFファイル: 162.3KB)

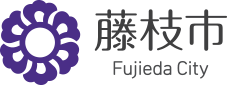

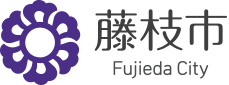
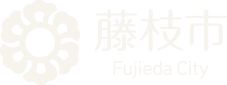




更新日:2024年05月10日