子どもの笑顔につながる特別支援教育を~「特別支援教育支援員」「学校生活支援員」を各校に配置~

藤枝市における支援員配置事業は平成13年度から開始し、平成23年度から全小中学校に配置しています。これまで「学校支援相談員」と「特別支援学級支援員」として各学校に配置していたものを、令和元年度から「特別支援教育支援員」として統一。学校の状況に応じて活用することができるようになりました。
令和2年6月には、新型コロナウイルス感染拡大による小中学校の臨時休校からの再開に合わせ、学習の遅れに対する支援や新しい学校の生活様式に対応した教育体制を整備するために40人を「学校生活支援員」として新たに配置。令和5年4月現在、計105人程の支援員を各校に配置し、子どもたちが安心して学校生活を送れるよう充実した体制を整えています。
支援員の役割
小中学校において、校長や教頭、特別支援教育コーディネーター、学級担任、教科担任と連携を図りながら学校のさまざまな場面で、児童生徒一人一人のニーズに応じた支援を行います。
特に、担任などの目や手が届きにくい部分を把握しながら、児童生徒への支援を充実させるのが特別支援教育支援員の役割です。
基本的生活習慣確立のための日常生活の介助
- 身の回りの整理・整頓における支援
- 給食の場面における支援
- 衣服の着脱における支援
学習の場面において困り感をもっている児童生徒の支援
- 教室にいられず出て行ってしまった児童生徒の安全確保と居場所の確認
- 姿勢が崩れてしまった児童生徒への声掛け
- 授業の流れについていけない児童生徒への支援
- 聴くことに困難を抱えている児童生徒への支援
学習活動や教室移動などにおける介助や支援
- 特別教室や体育館、運動場への移動支援
- 集団にはいられない児童生徒への寄り添い
- 制作や調理、自由遊びなどの補助
健康や安全確保のための支援
- 体育や理科、図工、美術、技術家庭など実技を伴う授業場面での支援による安全面の確保
- 担任などが教室を離れている場面において体調不良を訴えた児童生徒への介助
- 担任などが教室を離れている場面における児童生徒同士のトラブルの防止・安全確保
校外学習などの学校行事における支援
- 集団行動での不安感が強い児童生徒への個別支援
- 校外学習など慣れていない場所での児童生徒への個別支援
支援員の声

特別支援教育支援員は、子どもたちの支援はもちろん、先生方のサポートも大切な仕事の一つです。そのため、先生たちの言動の意図を常に意識し、それに対して自分がどう動くのかを考えています。それにより子どもたちにうまくアプローチができ、子どもの成長を感じることができたときには、大きな喜びを感じます。
子どもは一人一人異なった個性を持っています。保護者の立場になって、その子にとって最良な声掛けはどのようなものかというのも意識しています。
そうした対応によって、子どもとの距離が縮まって、子どものキラキラとした笑顔を見ることができたときが、特別支援教育支援員のやりがいを感じる瞬間でもありますね。

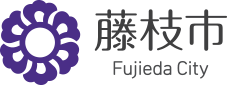

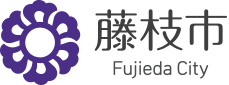
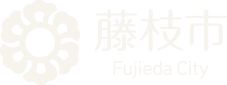




更新日:2023年04月01日