2024年の展示会
博物館企画展「龍(辰)の郷土玩具」

令和6年(2024)の辰年にちなみ、勇ましく威厳に満ちているものの、どこかユーモラスな龍(辰)の郷土玩具や和凧約150点を展示しました。
郷土玩具の名物作者たちが心を込めて手づくりした全国各地の龍玩具の造形や彩色を楽しめる展示となりました。
とき
令和6年1月5日(金曜日)~1月28日(日曜日)
文学館特別展 画業50年のあゆみ「黒井 健絵本絵本原画展」

人気絵本作家として第一線で長く活躍する黒井健(1947~)の画業50周年を記念した展覧会を開催しました。
黒井は、新美南吉の『ごんぎつね』や『手ぶくろを買いに』、間所ひさこの「ころわん」シリーズなど、300冊以上の絵本・児童文学の挿絵を描き続けてきました。
本展では、黒井の代表作を中心に、初期に手掛けた貴重なカットから、新作絵本の原画まで、黒井の原画約200点が一堂に会しました。
とき
令和6年2月3日(土曜日)~3月31日(日曜日)
博物館特別展「昭和のこどもたち展」石井美千子 創作人形の世界

藤枝市制70周年にちなみ、市制が始まった頃ー昭和30年代ーの子どもたちの日常と遊びの世界を、人形作家の石井美千子(1953-2023)が作った精巧な桐塑人形とジオラマで振り返りました。
石井の没後初めての遺作展となる本展では、「昭和のこどもたち」の主要40タイトルの作品を展示しました。写実的な人形たちで再現された懐かしい日本の原風景を通して、昭和の子どもたちの生きざまや、昭和の家族の姿を振り返りました。
とき
令和6年4月6日(土曜日)~6月9日(日曜日)
文学館特別展「コンドウアキのおしごと展」

「リラックマ」の原作者・コンドウアキの作家生活20周年を記念する原画展を静岡県で初開催しました。
コンドウアキは「リラックマ」「うさぎのモフィ」など親しみやすいキャラクターを生み出したキャラクターデザイナーであり、絵本作家としても活動しています。
本展では、デビュー作の『木からおりたミカン』から最新作の『ゆめぎんこう』まで、コンドウアキの作品を幅広く紹介しました。繊細な色彩で描かれた直筆原画を通して、親しみのあるキャラクターや、日常に愛しい時間を届けてくれる作品の数々をお楽しみいただきました。
とき
令和6年6月15日(土曜日)~8月18日(日曜日)
文学館特別展「金子みすゞの詩」

「私と小鳥と鈴と」・「大漁」などの詩で知られる童謡詩人の金子みすゞ(1903-1930)の生誕120年を記念する展覧会です。令和5年の東京会場に次いで、当館では全国で2番目に開催します。
金子みすゞは、西條八十に「若き童謡詩人の中の巨星」と称賛されながら、26歳の若さで世を去り、その存在は長く忘れられていました。しかし、没後半世紀を経て、矢崎節夫氏により512編の詩を収めた遺稿集が発見されたことを機に1984年、『金子みすゞ全集』が出版され、再び注目を集めます。
本展では、みすゞ自筆の遺稿手帳や当時の様々な資料、みすゞ作品の絵本原画などを通して、みすゞが情熱を注いだ童謡の世界を紹介しました。
【同時開催】没後10年 魂の俳人 村越化石展
とき
令和6年8月24日(土曜日)~10月20日(日曜日)
博物館特別展「戦国武将・岡部氏と朝比奈氏」

藤枝・岡部を発祥の地とする中世豪族(武士団)である岡部氏と朝比奈氏の歴史に当館として初めてスポットを当てて紹介しました。
岡部氏は源頼朝に仕えた鎌倉御家人の名族です。室町時代には両氏とも駿河守護・今川氏に仕え、数系統に分かれながら重臣として台頭します。戦国期には今川から武田・徳川へ駿河の国主が変わるなかで、一族の命運をかけて行動します。
本展では、戦国乱世を生き抜いた両氏の盛衰の軌跡や興亡を、貴重な歴史資料でたどりました。また、中世の岡部氏菩提寺だった「万福寺」(廃寺・藤枝市仮宿)の本尊・阿弥陀如来坐像【大阪府指定文化財】が、約100年ぶりに藤枝に里帰りしました。
とき
令和6年10月26日(土曜日)~12月8日(日曜日)
原田純夫動物写真展

世界的に活躍する藤枝市出身の動物写真家・原田純夫さんが撮影した写真作品を、11月のNHK-BS「ワールドライフ」で密着取材の特集番組「北米ロッキー山脈 断崖にマウンテンゴートを追う」の放映に合わせて展示しました。
自然豊かなロッキー山脈の風景と、そこで暮らす野生動物たちの生き方を鮮明に捉えた写真は、多くの来館者を魅了しました。
博物館特別展「大江戸の暮らしと町並み展」

令和7年の大河ドラマによって、大江戸の伝統文化に注目が集まりました。
本展では、江戸時代後期の商家や湯屋、庶民の長屋などを縮尺1/10、1/20で精巧に再現したミニチュア模型を70点以上展示し、大江戸の町並みや庶民の暮らしをご鑑賞いただきました。ミニチュア模型を製作したのは檜細工師の三浦宏です。もともと浅草の風呂桶職人だった三浦は、昭和55年(1980)、人形作家・辻村寿三郎から江戸吉原の妓楼「三浦屋」の製作を依頼されたのを機に、江戸時代の家屋や和船の忠実な復元に取り組み、亡くなるまでの40年で100点以上の作品を製作しました。
今回、呉服屋・湯屋・両替商・床屋・旅籠・船宿や庶民の棟割長屋、各町にあった高札場・木戸番・火の見櫓、各種の和船など、内部まで精巧に作り込まれたミニチュア模型を多数展示し、過去最大級の三浦宏遺作展となりました。浅草で育まれた生粋の職人技でよみがえった、江戸の町の風情や庶民の暮らしぶりをお楽しみいただきました。
とき
令和7年2月1日(土曜日)~3月30日(日曜日)
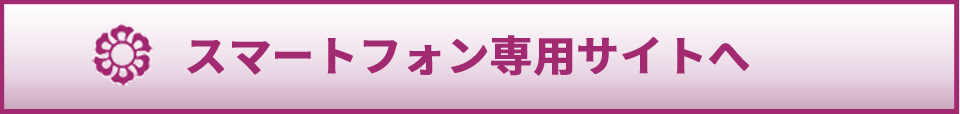

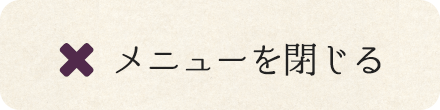


更新日:2025年04月01日