田沼街道とまぼろしの城(令和7年1月認定)
ストーリーと構成遺産
東遠江の海沿いの街道は「田沼街道」と呼ばれ、藤枝市内にも通っています。東海道藤枝宿から相良城をつなぐために作られた街道で、その名は大河ドラマにも登場する江戸時代の老中「田沼意次」に由来します。
賄賂のイメージが強いですが、その実は将軍から「またうどのもの(正直で律儀な人)」と評されるほどの為政家でした。
田沼意次が居城とした相良城は、わずか8年間のみの幻の城でしたが、意次の経営手腕によってこの地は大きく発展し、人々の記憶に強く残りました。意次を慕う人々がいつしか呼ぶようになった名が「田沼街道」です。
ストーリー「田沼街道とまぼろしの城」は、田沼街道と田沼意次に関係する史跡を中心に、牧之原市、藤枝市、焼津市、吉田町に所在する23件の文化財が構成遺産となっています。
その中でも、藤枝市の構成遺産(3件)について紹介します。
もう一つの東西街道
東西交通の大動脈である東海道は、京に向かい江戸を発ち、駿府を過ぎると暫時、山あいを行く。駿府から西に向かう街道は、 東海道の他にも海沿いを行く道がある。その一部は、いつしか「田沼街道」と呼ばれるようになった。「田沼街道」は、東海道の藤枝宿と東遠江の城下町・港町であ る相良を結ぶ道だ。街道は、多くが目的地や経由地を名に冠するが、この街道は人名に由来する。江戸幕府の老中を務め、相良藩主であった田沼意次である。
勝草橋 …史跡(未指定)

田沼街道の藤枝側起点にある橋です。藤枝宿の西木戸を経て瀬戸川を渡った袂から、田沼街道が分岐していました。江戸時代には橋がなく徒渡り(かちわたり)でしたが、明治時代になると橋が架けられました。
「またうどのもの」
徳川幕府9代・10 代将軍に仕え、史上唯一の老中兼側用人だ った田沼意次。「賄賂」のイメージが巷間に流布するが、その実は「またうどのもの(正直で律儀な人物)」と将軍に評された為政家である。意次の政策は、それまでの米中心の経済とは異なり、商工業の発展や流通の促進による経済の活性化を目指すものであった。近代化の先駆けとも言える政策の展開は、人々の生活にゆとりをもたらし、田沼時代と称される芸術・文化の花開いた新時代を生み出した。
相良の殿様と「田沼街道」
宝暦8年(1758 年)、相良藩一万石の大名となった意次は、明和5年(1768 年)に相良城の築城に着手。安永9年(1780 年) には、完成した相良城と領内の見分のため、生涯唯一となる領国 へのお国入りを果たすが、天明6年(1786 年)に失脚すると、相良城は破却され、田沼家は相良の地を去る。転封に伴い城と共に多くの記録が失われたため、実のところ、相良藩主としての意次の事跡は不明 な点が多い。「田沼街道」という名も、意次が名付けたものではなく、その在世時には、この呼び名さえなかった。しかし、天保13 年(1842 年)の古絵図には、その名が記されている。意次の死去から時を経ずして、この地の人々が自ずと呼んだ名が一般名称として浸透していた。人々が過去の領主を街 道名とした背景には、「越すに越されぬ」と詠まれた大井川の存在がある。
もう一つの、大井川越え
当時、相良から陸路で江戸を目指すには、牧之原台地を北上し、唯一の川渡しの場である金谷・島田間で大井川を渡って東海道を進むのが公式ルートであった。意次もこのルートを逆に辿り領国入りした。一方で、海沿いを進み、小山(吉田町)・相川(焼津市)間で大井川を渡り、藤枝宿に至る道もあったが、下流(下瀬)を渡ることは、御法度の非公式ルートであった。 しかし、意次は江戸への帰還時に、このルートを通り下瀬を超えた。この道こそ「田沼街道」である。幕府の重臣である意次が、この道を公式なルートとしたことにより、地域の流通が活性化し、街道沿いの産業が振興した。もう一つの大井川の渡河地点を持つ「田沼街道」。その名は、意次の功績や威光を称えるために、領民や街道沿いの住民が使い始め、この地に定着した。古絵図に記された道筋は、今も辿れる部分があり、記された地名も多く残り、意次が歩んだ街道の姿を体験できる。
幻の城「相良城」と意次の足跡
完成からわずか8年、近世で日本一短命な城となった相良城。往時のものは殆ど失われてしまったが、意次が整えた城下の町割は、現在の市街地の区画に引き継がれた。相良城の一部は、意次を慕う人々により散逸を免れ、領内や街道沿いの寺院に奉納された。断片的に残る石垣や土塁、移された建築部材や調度品、城下の面影を伝える町割を巡り、繋いで浮かぶのは、幻の相良城の姿であろう。 意次は、領内の寺社も手厚く保護した。将棋のタイトル戦が行われる牧之原市の平田寺もその一つである。平田寺は、田沼家歴代の御位牌を祀る香華寺として知られる。意次は将棋を嗜み、領国でも将棋が盛んとなった。牧之原市の旧家からは、領民が作った約 200 年前の詰将棋が発見されている。
岡部長慎奉納絵馬 … 美術工芸品(市指定)

藤枝市仮宿地域が発祥で、当時は岸和田藩主(大阪府)であった岡部氏が、相良城の接収役を無事務めたことを記念して、若宮八幡宮に奉納した絵馬です。
表面の風化により、描かれた馬は明瞭ではないですが、「泉州岸和田城主岡部美濃守藤原長慎」と墨書が残っています。
岡部長慎(おかべ ながちか)(1787~1859)は、和泉国岸和田藩の岡部家9代藩主にあたる人物です。
若宮八幡宮は岡部氏発祥の地と伝えられる仮宿地区に隣接した岡部町岡部にあり、岡部氏にかかわる伝説が残っています。岡部氏が駿河国から遠く離れた地にあっても、祖先ゆかりの神社を大切にしていたことがうかがえます。
大慶寺庫裡 …建造物(未指定)

大慶寺は旧東海道藤枝宿にある日蓮宗の寺院で、田中城の祈願所として信仰を集めていました。日蓮お手植えと伝わる「久遠の松」があり、静岡県の天然記念物に指定されています。
大慶寺の庫裡は相良城の破却後、売却された部材を転用したと伝わり、柱や梁、小屋組みの一部が当時のものであると言われています。
受け継がれる意次の遺産
不明な点が多い、意次の領国経営であるが、断片的に残る足跡からは、小さな港町・陣屋町だった相良は大きく変貌を遂げ、領内や街道沿いの地域も新たな時代を迎えたことがうかがえる。意次が、特に力を入れた領内の産業が製塩である。信濃に至る 「塩の道」の起点でもあった相良の海岸沿いに、塩田を作ることを奨励し、資金援助に加え、塩を年貢とすることも認めた。陸の道だけではなく、海の道にも注目した。湊を整備することで、領内で産出された石灰、特産物である塩や海草のサガラメ、梅干、鰹節、茶等も海路で江戸に運ばれることとなった。湊の交易は、地元の人々により引き継がれる行事となって名残を伝える。牧之原市内の神社で行われる「御船神事」は、相良湊の廻船問屋による海上安全・商売繁盛に端を発する行事である。意次が 進めた流通による地域経済の発展は、伝統行事に形を変えた。 食文化にも名残がある。牧之原市には、鰆の塩漬けや小魚の梅酢漬け、鰹をサガラメで巻いて煮た“めまき”などの郷土料理があるが、これらも意次が領内の産業に尽力した賜物といえる。 地元において意次は現在のまちの礎を築いた名君である。田沼家にちなむ名物開発や顕彰事業が盛んに行われてきた。その活動は昭和 40 年代に本格化するが、その元は「田沼街道」であった。 意次が認め、意次が歩き、意次が残した文化と遺志に触れられる全国唯一の道「田沼街道」。この道を辿り、城下をまわれば、意次が起こした新たな風の余韻を感じることができるだろう。
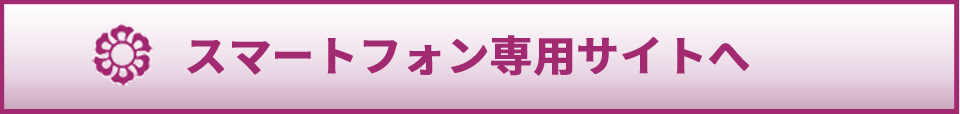

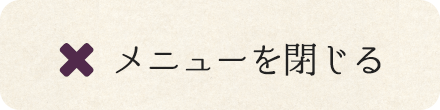


更新日:2025年08月16日