岡部名物「羊歯細工」

岡部名物「羊歯(しだ)細工」があなたの家にありますか。ほれ、しだで作った箱や盆などの細工物ですよ。原料のしだを刈(か)る人もなく、細工の手数もかかり、今はつくる人もいない。
羊歯細工が作られるようになったのにはこんな話がある。今から百年あまりも昔のことである。
内谷(うつたに)の里に裏白翁(うらじろのおきな)という人がいた。翁(おきな)だから年をかなりとった老人であろう。生まれつき才能のすぐれた人で、手先きも器用、書画や彫刻もすぐれていた。その技術の教えを乞(こ)う人が多く、弟子もたくさんいた。勉学のあいだを見て翁は時々西の山に登り英気を養った。山を登る道々、山には一面たくさんのしだが生えていた。
翁は弟子に話した。
「この裏白(羊歯(しだ)のなかま)は、ただお正月のお飾りに使うだけではもったいない。何とか使い道はないものか」
幾たびか山登りをするごとに使い道を考えた。
生まれつき非凡な翁のこと、この「しだ」の枝を細工に使ったら面白いものができるにちがいないと思い、手はじめに箸(はし)を作った。思ったよりも曲げたりする細工がしやすいことを知った翁は、しだの一本一本を火であぶって曲げたりのばしたりして、短冊掛(たんざくかけ)、色紙掛、衣紋掛(えもんかけ)、それから灰吹き盆(たばこ盆)などを細工してみた。
できあがった細工物を道行く人に売ったり、一部は江戸にも送ったりしてみたところ、雅趣(がしゅ)があるといって評判になり、そのため内谷はもちろん、その近くの部落でも作るようになり、果ては一つの職業とさえなった。細工の仕方もいろいろ考えられ、盆、状差し、菓子器やかご類までにひろげられた。ひところは中国、アメリカ等にも輸出されるまでになり、世界博覧会等にも出品し、金杯などの表彰を受けたりした。
手数がかかり、めんどうな細工仕事が現代人の気質に合わなくなったのか、細工の職業から離れるようになり、今はもう作る人がいなくなってしまった。
岡部名物しだ細工の物語りは、昔語りとなってしまった感がするが、裏白翁の彫刻は中ノ町(現在の内一地区)のいなり神社、碑(ひ)は光泰寺に残されている。もういちど「しだ細工を」の声が出ては来ているが、見なおしたい郷土の産業である。
「岡部のむかし話」(平成10年・旧岡部町教育委員会発行)より転載
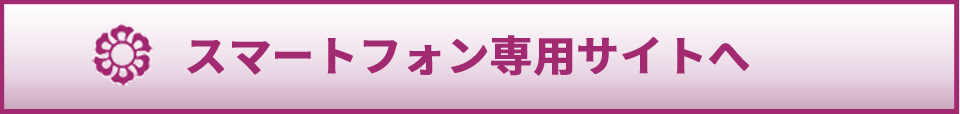

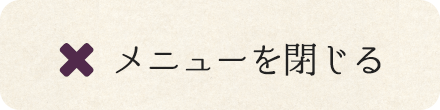


更新日:2018年10月08日