矢竹やぶ

朝比奈谷の殿(との)の部落の田の中に、ぽつんと一つの塚(つか)が残されている。ここの塚は広さが四平方米(メートル)ばかり、高さも一米(メートル)ばかりの小さい塚であるが、ここには竹が生(お)い繁(しげ)っている。
一見(いっけん)、山あいの静かな部落にも戦いの災(わざわ)いはまぬがれなかった。ここ殿の部落もこの地の豪族朝比奈氏の屋形(やかた)(家)があったからであり、部落の山の上には空堀(からぼ)りもある朝比奈城がある、ある時のこと、この山あいの地に合戦(かっせん)があった。敵味方入り乱れて互いに争い、敵方は反対側の小高い喜雲寺側の台地から矢を雨あられと射(い)そそいだ。勢いが落ちた矢は両軍の間の田の中に落ちてつきささった。
どのくらいたったことだろうか、不思議なことに、田に落ちた矢竹から根が伸びてきて繁り、一かたまりのヤブとなった。矢竹がつきささったのでこの竹は根のほうが細く、先になるにしたがって太くなっていったという。
里人もあまりにかわった竹であることから大切に保存して枯れないようにしていた。しかし竹はすぐ代(だい)がかわってしまいがちで、残っている竹はふつうの竹になってしまっている。
この「やぶ」を見かえるたびに、この里も昔は戦乱がいくたびもあったことを思い起こして里人は、平和の価値をかみしめている。
この文章は「岡部のむかし話」(平成10年・旧岡部町教育委員会発行)より転載
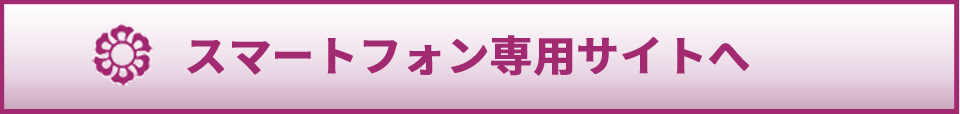

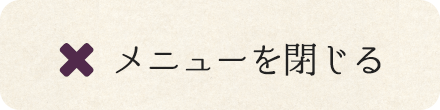


更新日:2018年10月08日