お杉とお玉と松沢

本郷から横添に通じる山道は、乗り物がなかった頃には東海道の近道として利用されて、かなりの人通りもあったという。この道の中程(なかほど)に人がまたいで渡れるくらいの沢があって、松沢と呼ばれていた。このところにかなり年数の発った二本の木があった。
いつごろ誰がつけたのかこの木は「お杉」「お玉」と呼ばれた。この二本の杉の木、玉の木にからむ物語があって、徳川時代から旅をする人々の口に言いつたえられていることがある。
二本の木の皮を削って誠に達筆(たっぴつ)で墨黒々(すみくろぐろ)と次のような歌が、何人とも知れず書かれてあった。
お伊勢ならお杉お玉といわれむに
何になる木(気)かここに松(待)沢
歌にうたわれたお杉お玉は、伊勢神宮の近く五十鈴川(いすずがわ)のほとりに、三味線(しゃみせん)をひきながらお伊勢まいりの人たちの喜捨(ぎしゃ)を求めていたという。その二人の名前は後々まで三味線ひきのその種の女たちの代名詞になって旅人の慰め語り草となって土産話(みやげばなし)となった。そのことがいつしか岡部の地方にも流れ来て、待沢の流れの二本の木にそのままつけられた。二本の木はもう枯れてしまって跡もないが、待沢の地名は松沢となって残っている。
「岡部のむかし話」(平成10年・旧岡部町教育委員会発行)より転載
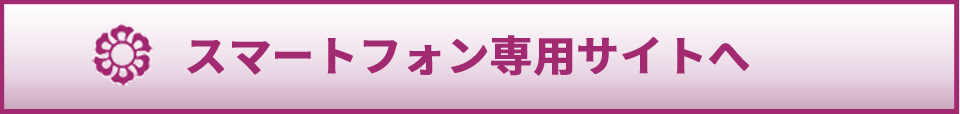

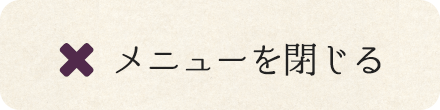


更新日:2018年10月08日